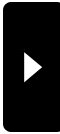2020年10月22日
〈serrated blade〉を攻略せよ
皆様こんにちは、まろ(仮)です。
今回のお題は「波刃を研ぐ」です、
どちらのご家庭にもあるとは限りませんので、興味の無い方はスルーして下さいませ。
― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

↑ 当家の波刃
上) ヘンケルス 「ブレッドスライサー(パン切り包丁)」
中左) ヴィクトリノックス 「Swiss Tool」
中右) G.SAKAI 「Vino(ソムリエナイフ)」
下) BOKER 「キャンプ用カトラリー」

↑ 「パン切り」拡大
尖った部分が対象に食い込み、窪んだ部分の刃で切り開く構造、
ナイフ、包丁のエッジをスケールアップしたようなものだが、
鋭利さを維持するにはこの一つ一つを砥がないといけない(=面倒くさい)

↑ 「パン切り」裏面
基本的に波刃のエッジは片側だけ削られている

↑ 「Swiss Tool」拡大、用途は主に「ロープカッター」
この位のピッチまでなら「ポケットストーン」の角で砥げなくもないが、
力の入り具合で「ムラ」になり易いんだよな

↑ 「Boker」拡大 ピッチが細かい
流石に「ポケットストーン」の角を動かすスペースが不十分だ

↑ 「BOKER」裏面
このベベルだけ砥いでも鋭利さは維持出来るがいずれ波が無くなる
どうしたものか・・・

で、思いついたのがこれ、
丸みを帯びた割り箸と串&研磨フィルム
どう使うかというと

巻きつけて(ズレない様に締め付け)、
棒鑢状にしてみる
波刃の径より細ければ面を砥げるはず
イメージは「接触している線で面を砥ぐ」感じ

より径の小さい面には串の曲面で

こいつには結構ギリギリの太さだった

バリが出たら裏面で落とす

結局「鋸の目立て」の様な作業になった(あれ程正確さは要求されないけど・・・)
老眼の身には厳しいので暫くは大丈夫であって欲しい

因みに「Vino」の波刃は曲面ではないので

ポケットストーンの角だけで砥げた
ワインの封を切るだけだし多少雑でもいいや(笑)
― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
今回もお付き合い頂き有り難うございました。
それではまた、まろ(仮)でした。
2020年09月13日
出番の多い貰い物(景品)
皆様こんにちは、まろ(仮)です。
以前「出番の無い貰い物」を紹介しましたので、
今回は「出番の多い貰い物」を紹介致します。
― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
長年通った「関市刃物まつり」(残念乍ら今年も中止と決まっているが)
「関アウトドアズナイフショー」と同じく楽しみなのが
メーカー、ディーラーさん巡り。
BBQやアウトレットセール、「中の人」なればこその内緒話etc・・・

そんな中、G-SAKAIさんの三角籤(買い物¥3000で一回)で当たった景品達
ジャンクセールも対象の上「空籤無し」なのが嬉しい

特にこの三つはキャンプ等アウトドアには欠かせない
尚、お皿は自前である、念の為

何処のブランドにOEM供給していたかは不明な分割式ナイフ
お約束の構成

真鋳の突起を穴に嵌め込み・・・、

フォークと缶切りを閉じるとロックするお馴染みの造作

ステンレス(おそらく420系)のブレード

ホロー(凹面)グラインドは好みではないが、網の上で肉を切るには充分
硬過ぎず砥ぎ直しも楽

一方こちらは「BOKER(独」)のカトラリー
おそらくG.SAKAIがOEMで製造していたものだろう

ナイフとフォークでスプーンを挟んで収納する機能的(?)な構造

ケースには調味料(塩・胡椒)入れが付属、使わないけど(笑)

ブレードには「ARGENTINA.STAINLESS」の刻印
元が1990年代の製品なので検索しても資料が見付からない

セレーション(波刃)は網の上だと引っ掛かるし、何より砥ぐのが面倒
しかし筋の多い安い肉でも良く切れるので重宝している
結局「使い途」があるかどうかなんだよな、道具だから
― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
今回はここまで、お付き合い頂きありがとうございました。
それではまた、まろ(仮)でした。
補記)「連休はキャンプ」という皆様(私もですが)、
くれぐれも三密による感染拡大にはご注意を
2020年08月15日
お盆休みも「Stay Home」
ウィルスの感染拡大は未だ止まず、仲間とのキャンプも九月の連休までお預けとなり、
実家からは「来なくて良い、と言うか来るな」とのお達しが・・・。
はい、お盆休みも「Stay Home」決定です。
まぁ「工作の時間ができた」とポジティブに考えることにしましょう。
― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

2017年購入の「あまご(服部刃物)」、実は些か不満があった
断面形状が微妙に「中膨れ=凸面(所謂コンベックスグラインド)」
荒事用の大型ナイフならともかく、ポケットサイズなら「フルフラット」の方が
「私的には」使い勝手が良い
腹を括って削ることにする

最初はダイヤモンドシャープナー、「砥ぎ」には粗いが今回の用途は「削り」
作った平面をアーカンサスポケットストーンで広げていく
凡その面ができたら耐水ペーパーで傷消し
これが頗る手間の掛かる作業で、本音では「余りやりたくない」
何故なら、「傷を消す事」とは、「その傷の深さ迄周囲を削り落とす事」であり、
今回削るべき相手は「熱処理済み=マルテンサイト(要するに硬い)組織」なのだ
が、始めた以上は納得いく迄やる(引っ込みつかないし)
先人曰く 「磨きの道は、修羅の道」

今回は強力な助っ人が「YOSI君鉄工所(仮称)」からやって来た
YOSI ) 「上手に使えば大幅時短になりますよ、
仕損じたら取り返しのつかない事になりますけど(笑)」
師匠、脅してくれるな。私は素人だぞ・・・

青いバフで赤い研磨剤(所謂赤棒)を、
白いバフで緑の研磨剤(同青棒)を使えば良いんだな?
やってやろうじゃないか(開き直り)

バフ掛け後 下地処理のペーパー掛けが不十分だったけどまぁいいか

因みに加工前、予想通り凸面にあった刻印はほぼ消えたけど、
欲しかったのは「記念品」ではなく「道具」なので気にはならない
太刀を「磨り上げ」て「打ち刀」にした大名・武将もこんな気持ちだったんだろうか?

早くキャンプで使いたい
― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
今回もお付き合い頂き有り難うございました。
それではまた、まろ(仮)でした。
2020年07月27日
「STAY HOME」 第二ラウンド
四連休は如何お過ごしでしたか?
私は例年なら遊び仲間と連泊キャンプなのですが、
ウィルス感染者が増加している現状に、【活動再開延期】を
幹事会で決定した為予定がありません。
妻に「何処か行く?」と尋ねると「観光地は怖いからいい」との返事。
はい、「自宅でゴロゴロ」決定です。
― ― ― ― ― ― ―
自宅で過ごすにも食材は要るのでスーパーへ
特売の【真鯛(養殖)冊】を発見した妻、
「手抜きじゃない昆布締め食べたい」との仰せ

当家の「手抜き昆布締め」とは、引いたお造りに粉末昆布茶を振り掛けた物
「化学調味料無添加」が肝
しかし今回は普通の昆布締めをご所望なのだ

「出汁昆布」で冊を包み冷蔵庫で一晩

削ぎ切りにして

昆布の「柵を包んだ面」を下にして器に敷き、お造りを並べる
昆布には予め大匙一杯程の酒を含ませておくと広げ易い

同じく未使用の面で挟んで冷蔵庫で半日も置けば出来上がり
一日掛けて作っても食べるには30分(笑)

使用後の包丁の手入れも忘れずに
此処まで打ち込んで気付く、
―刃物で何か切ってる記事ってこれが初めてじゃないか?-
― ― ― ― ― ― ― ―
今回もお付き合い頂きありがとうございました、それではまた。
以上まろ(仮)でした。
【追記】
ウィルスの感染拡大はまだ続くだろうと思います、
皆様も充分お気を付け下さいますように。
2020年07月07日
初めての作家さん物(但し詳細不明)
先月、コメント欄で交流のある某ブロガーさんが「お高いナイフでも・・・」等と仰っていたので
「お住まいの県内でカスタムナイフショーがあるので行ってみなはれ」と、
無責任に勧めてみました。
「いきなり【作家さんの集い】はハードル高いかなぁ?」とは思いましたが、「お腹一杯でした」
のコメントに「やっぱり・・・」と自責の念が沸きあがりました。
翻って「私の最初の【作家さん物】ってどれ?」と記憶を掘り起こしてみました。

1990年代半ばに街の刃物屋で購入したフォールディングナイフ


開長/刃長/刃厚 130/56.4/2.45(mm)
鋼材ATS-34 フレーム(ライナー)、ボルスター(口金)はニッケルシルバー、
ハンドル材は花梨の根瘤

ブレードシェイプ(形状)はドロップポイント
グラインド(断面形状)は半径の大きめなホロー(凹面)

しかし、作者に関する情報が全く無い
こちらのリカッソ(平面部)は空白
反対面には鋼材を示す「ATS-34」とあるだけ
店のご主人の仰るには
「左側面に深いツールマーク(研削痕)があるので銘を入れずに処分価格で放出したのでは?」
確かにプライスタグは一万円未満(¥8,000程)だった。

手持ちの【MOKI】のナイフと
アクション(開閉)のスムースさは互角
縁あって手に入れたのに、作者さんに「これいいね」と言えないのが残念。
そして「【作家さん物】はショーで本人から購入しよう」と思う様になったのである。
補記)作家さんがショーのテーブルに並べるのはあくまでサンプルであり、
ユーザーと作家さんが作り上げてこその「カスタムナイフ」だと私は思っている。
今回もお付き合い頂き有り難うございました、
それではまた、まろ(仮)でした。
2020年06月09日
出番の無い刃物達 ~包丁編~
皆様こんばんは、まろ(仮)です。
今回は当家の【出番の無い包丁】を紹介します。
出番の無い理由は様々ですが、「まだ無い」物と
「控えに回った」物とがあります。
尤も、「数が多過ぎる」のが最大の理由なんですが(笑)。
それでは御笑覧ください。
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

「正広」(上)と「兼常(グランシェフ)」(下)
何れも八寸(≒240mm)牛刀、頂き物、関市(岐阜県)製、
「モリブデン/バナジウム系ステンレス」という点迄共通している

八寸の牛刀は当家一の激戦区であり、
この二つは妻的に「握りがしっくり決まらない」とのことで
MISONO・兼房(共に前回投稿)の後塵を拝している
「その内ハンドル削るよ」と言ってそれっきり、
現在の主力が砥ぎ減ってからでも良いか・・・

服部刃物(刃物ヲタ的にはHattori)の「積層七寸」(上)と
杉本の「八寸牛刀」(下・妻所有)

「服部」はV金10号を心材にした積層鋼【所謂】ダマスカス
「関住唯知郎作」の銘が鏨で施される
「出番が無い」と言うより「老後の楽しみに取ってある」感じ(笑)
一方「杉本」は妻が商売道具にしていた炭素鋼(工具鋼・JIS/SK)
前述の通り八寸の牛刀は激戦区の上、
「(研げば)鋭いんだけど長続きしない」ので予備役に・・・、
最近の刃物用ステンレス鋼は硬度(≒刃保ち)では
炭素鋼を上回る事が多い
典型的な例を紹介すると

ペティナイフが二つ
上は前回で紹介した「G・SAKAI 5インチ(≒130mm)鋼材ATS-34」
下は「杉本 五寸(≒150mm)炭素鋼(JIS/SK)」
「切れ味の繊細さ」なら炭化物の細かい炭素鋼だが、
「鋭利さの持続性」では高硬度(HRC60超)のATS-34が圧倒する
主な使用者(妻)は耐蝕性を加味してATS-34を選択、
「杉本」は予備役に編入となった。

妻所有の「久元」尺刺身包丁
前回紹介した私の「兼重(?)」と完全に被る上、
現在「造り引き担当」が私の為出番無し、
「その内こっそり試してみたい」と思っている(笑)
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
今回もお付き合い頂き有り難うございました。
それではまた、まろ(仮)でした。
2020年05月17日
「STAY HOME」の過ごし方
皆様こんにちは、まろ(仮)です。
「STAY HOME」の大型連休は如何お過ごしになりましたか?
私は当初「ウチの刃物全部砥ごう」等と思っておりましたが、
初日・二日目と所用で外出した為、
「先ずは(使用頻度の高い)包丁からだな」と規模縮小しました。
― ― ― ― ― ― ―

先ずは準備、シャプトンの砥石各種
写真左から 粗目・中粗・中仕上げ・仕上げ・超仕上げ
上の両面ダイヤ砥石(№400/1000)は面直し用、粗目も同様

纏まった休みでもなきゃやる気にならない面直し
使い古しのダイヤ砥石で砥面を水砥ぎする
ペースト状の遊離砥粒は革の床面や古デニムにでも塗っておけば
手軽なタッチアップツールになる

一番使用頻度の高い中仕上げ
使ったらその場で直しときゃ良いんだけど・・・。

今回研ぐ洋物 上から
G・SAKAI 「ペティナイフ」 5インチ(≒130mm) 鋼材 ATSー34
兼房 「牛刀」 八寸(≒240mm) 鋼材 V金一号(VG-1)
MISONO 「牛刀」 七寸(≒210mm) 炭素鋼(SKらしい)
MISONO 「牛刀」 八寸(≒240mm) 16Crステンレス(440Aか?)
MASAKANE 「牛刀」 尺(≒300mm) ステンレス(詳細不明、420か?)
包丁メーカーの物はサイズが寸(約30mm)刻みなのに対して、
ナイフメーカー(G・SAKAIのみ)はインチ(約25mm)刻み
MISONOの炭素鋼七寸のみ妻の所有品
ペティと八寸二本は「関市刃物まつり」で購入
MASAKANE は貰い物だが、同社は廃業しているため資料が無い

同じく和物 上から
兼重(?) 「蛸引き」 尺 炭素鋼
菊秀別作(誂え) 「菜切り型片刃」 六寸(≒180mm) スウェーデン鋼
十三秀(とみひで) 「出刃」 六寸 ステンレス(詳細不明)
兼重(?)は貰い物、「堺モノ」である他は不明
十三秀は「刃物まつり」で購入
菊秀のみ妻所有、自前の刃物が幾つもあるのに、
気付けば私の刃物が「お気に入り」になっている

作業中の写真が無くて恐縮だが、砥石で砥ぐときは、
「刃を前にして押し、手前にして引く」スタイルである
(ペーパーやフィルムを使う時とは逆になる)
上の写真の向きのときには引いている

洋物砥ぎ上がり

和物砥ぎ上がり
でも出番の少ない包丁がまだまだある・・・
「そのうち」にしておこう
― ― ― ― ― ― ―
去る5月15日、ナチュログに越して来て一周年となりました。
こんなニッチなブログにお付き合い下さっている皆様に感謝します。
それではまた、まろ(仮)でした。
2020年03月29日
野外でシャープニング
皆様こんにちは、まる(仮)です。
新型コロナウィルスの所為で外遊びも出来ない昨今ですが、
気分だけでも、と野外でのシャープニングについてお話しします。
「態々外で砥がなくても」と思われる方もおられるでしょうが、
刃物も使えば消耗しますし、
「後で砥げば良い」と思えば安心して使えます。
― ― ― ― ― ― ― ― ―

ざっと広げたツール
左上二つ(革ポーチ入り) アーカンサスポケットストーン
右上 耐水ペーパー№2000と研磨フィルム
中 セラミックスティック(砥ぎ棒)
左下 ダイヤモンドシャープナー及び鑢

ダイヤモンドシャープナーと鑢
シャープナーは随分磨耗している様に見えるが、
このくらいでないと目が粗すぎる(正直これでも粗い)
鑢は大きく欠けた時の為に携行、まず使わない

裏の凸面はセレーション(波刃)に使用

セラミックの丸棒 太さ1インチ(≒25mm)

片側を握り、もう一方を何かに当てた状態で使用する
慣れたら空中でもできる

軽さなら耐水ペーパーと研磨フィルム、

鉈の木鞘を台替わりにして

本当はペーパーと鞘を手で押さえたいのだがカメラが・・・
研磨フィルムも同様に使う

持ち歩くことを前提にした「ポケットストーン」
米アーカンソー州産の天然砥石だが殆ど枯渇したらしい
成分は石英の微粉末、地質用語で「チャート」と呼ばれる
写真上は「細目」 下は「極細」

片手で持ち、もう片手のナイフを砥ぐ
「アーカンサス砥石には油」と言う人が多いが
私は敢えての水砥ぎ
― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
野外で砥ぐ為の道具等を紹介いたしました、
記事書いてて尚更外に出たくなった私です。
尚、紹介した方法は全てタッチアップ(鋭利さの一時的回復)ではなく、
通常(自宅での)の砥ぎと同等の効果を求めたものです。
今回もお付き合い頂きありがとうございました。
それではまた、まろ(仮)でした。
2020年03月22日
「Folding Sportman」をもう少し
皆様こんにちは、まろ(仮)です。
先日友人HIROさんに「Randall」をお借りした際、
「ネタに」とあれこれ拝借しました。
今回はその中から「Gerber Folding Sportman(以下FS)」の
バリエーションをご紹介致します。
― ― ― ― ― ― ― ―

写真左から
① FS-Ⅰ シリーズ末期モデル(推定)
② FS-Ⅱ スタッグ(鹿角)ハンドル
③ FS-Ⅱ V-Steel
④ FS-Ⅱ シリーズ末期モデル(推定)
⑤ FS-Ⅲ 同上
※)①、②、③ はHIROさんより借用、

サイズ「開長(刃体長)×刃体幅×刃厚mm(約)」は
① 155(68)×18×2.4
②、③、④ 200(92)×18×2.4
⑤ 230(100)×24×3.0
ブレードは全てフラットグラインド
モデル№はⅠ・Ⅱ・Ⅲ となっているが、
発売は何故かⅡ・Ⅰ・Ⅲ の順である

① FS-Ⅰ
シェイプ(刃体形状)はドロップポイント、鋼材440C
ベベルストップ(研削部後端)が段になっているのが
シリーズ末期とした根拠(④・⑤と同形状)

写真上から④、③、②
ブレードシェイプ(刃体形状)はトレーリングポイント
ドロップポイントのモデルも存在するが入手する機会が無かった
最初期のモデルにはブレードがゾーリンゲンで作られた物もある
ブレードのバリエーション(シェイプ・鋼材)があるのはFS-Ⅱのみ

② FS-Ⅱ スタッグハンドル 鋼材440C
ベベルストップは曲面(凹面)なのが比較的古いモデル
造形の美しさならこれだが欠点もある(後述)

③ FS-Ⅱ V-steel
V-steel とはゾーリンゲン(旧西独)の「ヴァスコウェア社」製造の
冷間プレス金型鋼で、D2(JIS/SKD11相当)に近い組成らしいが、
同社は既に廃業している為確証は無し
末期にはドロップポイントで作られたが、総数は決して多くない

④ FS-Ⅱ 末期(推定)モデル 鋼材440C
リカッソ(刻印のある部分)が短く、有効刃長が一番長い
余談だが440Cは元々ベアリング用の鋼材で、1970年代迄は
高級鋼材の代表だった(勿論現在も優秀さは認められている)

② 「スタッグハンドル」のブレード
ベベルストップが曲面の為、有効刃長(エッジ部)は
刃体長に対しやや短い

③ 「V-Steel」のブレード
リカッソには「エクスカリバー」とV-STEELの刻印
有効刃長は②と④の中間

④ 「末期(推定)モデル」のブレード
リカッソを狭めた分、有効刃長は最大
チョイル(刃元の小さい凹部)はDIY、個人的には
あった方が使い易い

② の刃元
普通の水砥石で砥いだら変な傷が一杯付きそうだし、
有効刃長は更に短くなっていきそう・・・
まぁ自分のじゃないので心配しても仕方ないんだけど

③ の刃元
刻印が多い分リカッソも大きめ、
必然的に刃長は限られる

④ の刃元
造形の美しさはともかく、
私が実用性で選ぶならシリーズ末期モデル

① の刃元
④ と概ね同じ
FS-Ⅰのみハンドル周囲が面取りされていない

⑤ の刃元
④ と同様にチョイルを加工してある
並べて撮影しないとFS-Ⅱ、Ⅲの区別がつかないかも?
― ― ― ― ― ― ― ―
所謂「Old Gerber」のFSシリーズ、主にFS-Ⅱの
バリエーションについて紹介しました。
他にも幾つかお借りしたので、その内機会を設けて
ご紹介したいと思います。
今回もお付き合い頂きありがとうございました。
それではまた、まろ(仮)でした。
※)HIROさんには改めて御礼申し上げる次第です。
2020年03月15日
出番の無い貰い物 ② -謎の多徳ナイフ-
皆様こんにちは、まろ(仮)です。
今回は「そのままでは使い難いナイフを何とかしよう」とした
苦闘の記録です。
― ― ― ― ― ― ― ―
2017年の「関市刃物まつり」、某ディーラーさんにて
「お越しのお客様全員に進呈しております」
と頂いたツールナイフ

一目で判る「Swiss Army」のコピー品

「Se-Ba」ってのがブランド名か?製造国等の表記は無し

開いてみる ツール構成は左から時計回りに
① 缶切り(ウェンガータイプ)
② ブレード(やや箆状、好みでないシェイプ)
③ 鋏(ヴィクトリノックスタイプ)
④ ドライバー(マイナス)兼栓抜き
⑤ ドライバー(フィリップス)
⑥ 爪やすり
⑦ コークスクリュー
①、④、⑦ は本家スイス製と比べると随分華奢な印象

反対面 シェル(貝殻)のインレイがあるが、隙間が気になる
この辺で朧げな記憶が浮かんでくる
「昔ナイフマガジンか何かに載ってなかったか・・・?」
そして気になり出すと際限なく粗ばかり見えてくる

ブレード ネイルマーク(爪掛け)が普通と逆の面にある
右手親指の爪を掛けて開く私には頗る勝手が悪い
一瞬「左利き用か?」とも思ったが、
他のツールのネイルマークは反対面にある、何故?
キック(研ぎ減り等で刃先が露出した際調節する為の削り代)も無い
デザイン(設計)した人物は素人か?

比較用に「Victorinox Camper」
ネイルマークの位置はこちらが一般的

(参考 Gerber FS-Ⅲ)
矢印の指し示す部分が「キック」
砥ぎ減ってポイントが露出したらここを削る

収納時ブレード側面がライナー(フレーム)と接触しており、
開閉時擦れる為ネイルマーク付近に傷がある
設計の不備か加工精度の低さか・・・

ブレードはライナー式のロックが付いているのだが、
私の(写真右)物は力を入れて開かないとロックバーが掛からない
品質管理はどうなっているのか?
(写真左の物はYOSI君より拝借)

青ペンの先「ロックしている」 赤ペンの先「ロックしていない」

サイズ的には使い勝手の良さそうな鋏なのだが

困った事にこれが「切れない・・・」
ピボットのカシメが甘い上に刃の反り(左右)が無い為

余りに腹が立ったので力尽くで反らせる

何とか「多少マシ」にはなった
が、カシメが甘い(ガタがある)刃元近くでは切れない

今一つ気に入らなかったブレードも削って整形したが・・・

フィリップス(+)ドライバーを開くと、

ポイントが僅かだが出っ放しになる事が判明
しかもキックが無いので引っ込められないし、
研ぎ減りすれば更に露出が大きくなるのは明白
弾みで怪我でもしたら詰まらないので本品は「封印」と決定
「折角頂いたのに使える物に出来なかった・・・」と
徒労感に苛まれた私であった
― ― ― ― ― ― ― ―
当記事は貰い物にケチをつけるのが目的ではありません。
しかし良くない物を「良くない」という事も時には必要でしょう。
尤も「売り物になるのなら無料で配ったりはしないよな」と、
今となっては思うのでした。
今回はこの辺で、
それではまた、まろ(仮)でした。
注)現在同ディーラーさんの取扱い品リストにこのブランド名は見当たりません